| 4/4 |
|
菌遊屋の独り言—キノコに始まりキノコに終わる— 萩本宏 |
| 前にもどる・・・3/4へ |
| 私は、その5年前に応植を去っていたので、その本当の理由は知りません。応植にいても今村先生を除いた3人の教授方が密室でお決めになることですから分かるはずがありません。一見、教授の大幅な若返りです。これは決して悪いことではありません。理学部の動物学科や植物学科では教授の年齢に近い方は、後継を後輩に譲っておられました。問題なのは、その推察される動機とその人事がもたらした結果です。後継者のT氏は研究一筋の方で、今村先生の最晩年までよく正月に先生のご自宅でご一緒しましたが、教授をT君と呼ぶ3人を配下において講座を思い通り運営することは、3人のご協力のもとでも容易ではありません。「名誉教授が3人おられるみたいだ」と言った先輩がいました。T氏も困難な事態は十二分に推察されていたはずで、当然教授就任の要請は固辞されたと思います。 理由は若返りではなさそうです。あくまでも私の推察にすぎないので、間違っておれば大変失礼ですが、応植は農学の基礎になる高等植物の生理学をやるところで(高等植物だけが農学の分野ではないことは現在では極めて明白ですが)、菌類や菌根はおろかクロレラ、ヘルミントスポリウムやセンチュウなどを野放図にやられては困ると思われたことや濱田先生の思考のスケールの違いではないかということです。私は、研究対象を院生・学生の好きなように無制限に拡げるのは、研究室全体としては、教育、研究予算、研究成果、研究室の学会におけるプレゼンス、学生の就職などにおいてマイナスであると思っていました。研究範囲をどのように限定するかは教授のフィロソフィーの問題であり、研究室のポリシーとして具現化されるはずのものです。それで研究のある程度の集約化の必要性を恐る恐る濱田先生に申し上げたことがありましたが、先生は「そんなことしたら『一将功成りて万骨枯る』だぞ」と仰いました。 応植の後継人事問題の予兆は、はるか以前からありました。1960年の卒論発表会で前記のY君がクロレラをテーマにした卒論研究を発表した時にA教授から「その研究は応植とどのような関係があるのだ」という質問がありました。私には「応植の範囲を逸脱した研究ではないのか」と聞こえました。その教授はT氏の就任後も「マツタケの研究は駄目だな」と言っておられました。私が会社へ行くと決まった時に、下等族殲滅作戦の始まりだと穿った見方をした後輩がいましたが、私以外にも敏感な人がいたということです。このように「農林生物学とはなにをするところか」という議論は、学科設立当初から常につきまとっていたようです。通常は、「農学の基礎をやるところだ」ということになっていましたが、なにが農学の基礎かと議論すれば明快な答えが得られるのでしようか。 『京都大学農学部四十周年記念 歴史を語る』(1964)にアメリカの高校・大学を卒業し、現地で職についていて京大に招聘された昆虫学講座の初代教授・理学博士の湯浅八郎氏(同志社総長に2回就任、後に国際基督教大学初代総長)が次のように書いておられます。「(農林生物学教室は)教室の内容・教育理念・指導方針・教授と学生との人間関係においてもかなり進歩的であり、革新的でさえあったといえよう。」「異色のある農林生物学教室で、いわば最も忠実にわが国学界の伝統を重んじ、人事の統制を厳にし、克明に研究テーマを守り、重厚な学風の樹立に努力して成功されたのは逸見教授であっただろう。万事に自由放任に終始した私にとって、植物病理学講座は常に驚嘆と尊敬の的であった。」「農学部に属する講座であるから応用昆虫学に重点を置くべきであったかも知れぬが、私は害虫そのものについてすらもむしろ実用的な技術や知識よりも昆虫を活きた生物として生態学的に観察し理解し研究し対処することが、最も根本的な研究の仕方だと考えていた。」「農林生物学という看板に対してはやや不忠実という批難があり得るといわねばなるまい。もっとも私は今日なお当時の私の理解や方針が本質的に間違っていたとは考えない。ただ批判の余地があったなと反省しているのである。」 菌類や菌根の研究は立派な農学の基礎になる研究であり、同時にキノコや林木の生産そのものに直接役立つ応用研究でもあります。今やわが国のキノコの生産額は他の林産物を凌ぐほどです。さらに熱帯林も含めた森林の保全、里山の再生、日本の伝統的景観の維持など広い範囲に深く関わっています。そのことを最も雄弁に語っているのは、小川眞君の日本林学賞(1980)、日本人最初のユフロ(国際林業研究機関連合)学術賞(1981)、日経地球環境技術賞(1998)、日本菌学教育文化賞(1999)、愛・地球賞(愛知万博)(2005)など数々の受賞です。私が職業としていた農薬の分野では、近年、マツカサキノコモドキと同属(Strobilurus属)のマツカサシメジからstrobilurin AおよびBという抗菌物質が発見され、その様々な誘導体が農業用殺菌剤として開発、上市されています。様々なキノコ由来の物質が研究され、人々の役に立っている例は沢山あります。 近年、基礎研究と応用研究を区別することは益々難しくなっています。有用動植物や病害虫を研究材料にしておれば応用研究でしょうか。そして、それは農家の病害虫管理に役立つのでしょうか。植物病理学、昆虫学、雑草学を標榜する研究室の成果がそのまま農家の病害虫・雑草管理に役立つことは、今日では稀なことです[萩本宏『生物資源から考える21世紀の農学』第3巻(2008)第9章2(4)]。大学に対して農業に直ぐに役立つ研究を要求するのであれば、理学、文学、芸術学のうちで人類の知的財産の形成が主な学問、当面役に立ちそうにない純粋研究とでも言うべき分野や教育研究だけを国立大学法人に残して、他の領域はそれぞれ関係省庁所管の独立行政法人に移したうえで既存の研究機関と統合すればよいのです。私は、生物学が生命科学として抽象化・記号化・普遍化され、生き物の姿が見え難くなる方向にあって、大学における応用研究は具体的・個別的な生き物や生態系の姿を描くことによって農林・水産技術、食品技術、環境保全技術などへの活用の道を開くもので、基盤研究とでも呼ぶべきものだと思っています。 基礎研究と応用研究の多くは、純粋研究と実用化研究ないしは開発研究を両極としてその中間に位置しており、個々の研究が基礎研究か応用研究かを分けるのは研究者の意識の問題であるとすら思えるのです。資源に乏しいうえに韓国や中国などの新興国に追われるわが国は、目先の改良的発明ではなく、大きな領域を包含する発明・発見に基づく高付加価値製品とソフトや情報などの形のないもので生きていくことを考えなければなりません。この基盤を担うものこそ大学であるべきです。「基礎深ければ応用広し」が私の持論です。原子と遺伝子の基礎及びそれらの応用研究の歴史がそのことを如実に示しています。 戦前、水稲の耐冷品種陸羽132号を育成した某国立農事試験場長が木原教授の染色体の研究を指して「理学部でやることだ」と非難されたという話を聞いたことがありますが、現在の育種学をみればいかに的外れの批難であったかが分かります。昆虫学研究室でも湯浅教授が学生に海中に棲む微小な双翅目昆虫や渓流の水生昆虫の研究(今西錦司氏や可児藤吉氏の棲み分け理論に発展)など農業に関わりのない研究を好きなようにやらせたことが祟ったのか、教授の推薦された後継者は拒絶されたそうです。そして、二代目教授が㈶大原奨励農会・大原農業研究所から就任し、農業に直接関わりのない研究を締め出したことで、後に立派な業績をあげる今西氏、岩田久仁雄氏、森下正明氏などが卒業後、理学部大学院に移ってしまったと言われています(大串龍一『日本の生態学‐今西錦司とその周辺』1992)。 三代目のU教授はその際に昆虫学講座に残られた方だそうですが、無論、これは一つの見識です。U教授について大串氏は前掲の著作で「U(本文は実名)の指導方針は研究対象と方法をきびしく限定して、典型的な実験生態学の研究室になっていた。(中略)また本当の自然を知りたい学生に狭い対象と方法を強制することによって、個々の学生の創造的能力を圧殺するという批判もあり、不満をもつ学生も少なくなかった。しかしUは一見おとなしそうな、むしろ気弱な外見にもかかわらず、この点では頑固に自分の方針を通した。それはちょうど同時期の理学部の動物生態学研究室の教授の宮地の自由奔放な研究室運営とはっきりした対照を示した。」と書いておられます。この文章の動物生態学研究室はそのまま応植に置換できます。U教授はご自分が理想とされる研究室のあるべき姿を応植にも強要されたのでしようか。 濱田先生は、他の人が考えないようなことを考えられることが往々にしておありでしたので、教授方は「農林生物学とは」という命(迷?)題と併せてこのような人物を教授にすると和を欠いて学科の運営が円滑にゆかないと考えられたのかもしれません。また、先生のグループの院生・学生は様々な分野にインベーダーのように侵出するのではないかと危惧されたのかもしれません。さらに、農学を自然科学でもなく、人文・社会科学でもない第三領域の学問とみる他の学科の教授から応植での研究課題と院生・学生に対する対応について批判があったのかもしれません。もし異質性の拒絶や自分達の領域が脅かれるというような杞憂が原因だとすれば、恐るべき肝っ玉の小ささです。 教授方は、T氏をどのように説得されたのかは無論知るよしもありませんが、私はT氏も被害者だと思っています。T氏は教授でありながら自ら実験をされていたようですし、退官後も他大学に再就職されることなく、個人の実験室を借りられて花芽形成の研究に勤しんでおられたほどの研究一筋の学者です。助教授に就任されておられれば、教授達を標的にした学園紛争に遭遇されることもなく、研究に専念されて花芽形成の研究は大いに進んだはずと残念に思います。要するに高等族と下等族の関係を逆にするだけでよかったのです。濱田先生とT氏との年齢差は17歳と十分にあり、すべてがうまくいったはずです。 新しい学科や講座がどんどんできた1960年台から70年台にかけて講座が1つも増えなかったのは農林生物学科だけだったように思います。反面、増えたのは学科の定員9名が15名になったことと、それにもかかわらず競争率は十数倍の最難関学科になったことでした。この時代に応植を高等族と下等族の2講座に分割し、衣川氏、S君や0君などに農芸化学系の人材も混じえて植物菌類共生学講座を開設する、もっと欲を言えば全学部横断的な大学附属菌学研究所を編成し、キノコ栽培所でも附属させて研究費を稼げればさぞ素晴らしい菌学・菌根学研究の場ができたろうにと思います。当時の農林生物学科の教授陣にそのようなことを期待するのは痴蕈(?)の夢ですが・・・。 今村先生は七高文科から東大法学部に入学され、1?年後に「自分には向いていない」と言って京大理学部に転学されるという異色のご経歴の持ち主です。私は後任人事の一件については先生の晩年に若干のお話を伺っていますが、後任者については、濱田先生と思い込んでおられたようです。それに、先生はマネジメント下手を自認しておられました。先生は、私や私の兼務先へのご対応の例でも明らかなように、万事に大変遠慮がちでした。そのような先生に「なぜ念には念を入れて根回しをしっかりとなさらなかったのですか」とは申し上げ難いことでした。「当時、O君と廊下ですれ違ったら顔をそむけて通り過ぎたよ」と仰っておられたのが今も記憶に残っています。 濱田先生は闊達で、地位、名誉、金銭など俗なるものには無論のこと、ご自分の命に対してすら淡泊でした。お一人超然としておられるところがありました。弟子が論文原稿を先生との連名にしておくと「君が一所懸命やったのだから」と言ってご自分の名前を消してしまわれたほどです。このような人物は俗世間では一番始末が悪くて持て余されるものです。群れるのを極端に嫌う個性の強い弟子たちは、就職のないのを十分に承知のうえで先生のお人柄に惹かれて集まってきたのです。今村先生が「骨のある奴は皆、濱稔の方に行ったね」と仰っていました。「皆」は大げさですが、そのような傾向はうかがえました。 この人事の最大の問題は、濱田先生の処遇ではなく、T教授の困惑や難渋でもありません。日本の否、世界の菌学の有力な拠点を潰してしまったことです。生物多様性や物質循環が重要な問題と認識されるようになっている今日、益々残念なことです。この人事で高等族の研究がいやがうえにも進歩したということもなさそうです。このような結果をみると下等族を潰すこと、さらに濱田先生を排除して統制的な教育・研究を行う学科に仕上げることが目的であったとしか思えません。これは学問に対する冒涜です。そのことは、濱田先生の弟子たちの活躍をみれば極めて明白です。 |
| このような暴挙を主導したと推察されるお二人の教授はもうこの世にはおられませんが、ご存命中にこの結果をみてどのように思っておられたのでしようか。今や濱田先生の弟子達もあらかた退職してしまわれましたし、幾人かは冥界の人です。退職された多くの方は今なお活躍しておられるようですが、孫弟子の時代に移りつつあります。私も含めて大勢の弟子たちがよくお邪魔した想い出の多い北白川の先生の邸宅も昨年夏に更地になり、今年になって新しい持ち主による邸宅の建設が始まっています。「昭和は遠くなりにけり」です(写真16)。 今関六也氏は早い時期から菌類、それも日頃は食用菌や植物病原菌などとして注目されることのない「ただの菌類」が地球生態系の物質循環に大きな役割を果たしている不可欠の存在であることを様々な機会に啓蒙してこられました。それから半世紀余、生態系や生物多様性の重要性が叫ばれながら、菌学研究を推進するような科学技術政策は不在です。それどころか研究拠点は次第に少なくなっているように思えます。せめてもの救いは、この間、各地に菌類談話会やキノコ愛好会などが百近くもできて、私の推定で1万人くらいのアマチュアが活動していると思われることです。全国の植物病理学や害虫学の研究室のいくつかは、病原菌や害虫から解脱して、ただの昆虫や菌類が生態系の中で果たす役割の解明にも取り組む必要があると思います。 |
 写真16 濱田邸で開催される恒例の濱田先生 主催の懇親会。他講座からの参加者 もあって大勢の人で賑わった。中央 は濱田先生、右側は著者 (1960年1月23日) |
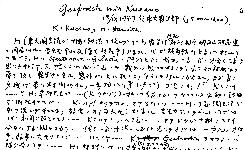 写真17 濱田稔先生が1947年9月18日に 初代日本菌学会会長草野俊助博士 と面談された際の先生の対談記録 カードの1枚目 |
応植は、T氏のあと、たまたま私の高校、それも生物部の後輩で理学部化学科生化学講座の助教授のI君に引き継がれ、1996年の学部改組に伴い大学院生命科学研究科に移行しました。さらに彼の後継者は東大理学部出身で京大理学部を経由して就任され、花芽形成の分子機構の研究などを精力的に進めておられるようですが、私は面識がありません。濱田先生がご退官になって後、大学に残された先生の書籍やJulius Oscar Brefeld (1839 -1925)の菌学の大著などはどうなったかと心配したりしていますが、余計なことかもしれません。 学者、特に理科系の学者がこの世を去られるとご遺族は書籍などの処置にお困りになるのが常ですが、弟子が困惑するのは原稿やメモ書きなど恩師の遺産です(写真17)。捨てる訳にはいかないし、さりとて残しておいてもどうしようもありません。なんだか神様が宿る神社のお札を処分しあぐねているような気持ちになります。郡場先生の遺稿は、タバコの箱に書かれたメモまで濱田先生が丹念に調べられて、『郡場寛遺稿集』(1957)として郡場寛遺稿集刊行会から、またご健在な頃の弟子たちとの会話は、濱田先生の克明な記録により木原均編『郡場寛博士 生物学閑話』Ⅰ-Ⅳ1962-1970)として出版されていますが、誰にでもできることではありません。 |
| 私は、昨年の秋に高貴高齢者になりました。実は、私が生まれた1934年のこの日は、湯川秀樹氏(27歳)が、東大で開催された日本数学物理学会(日本物理学会の前身)において “On the interaction of elementary particles.Ⅰ.”の演題で講演をされた記念すべき日です。私にはなんのご利益もありませんでしたが・・・。この講演は翌年、最初の論文(28歳)になりますが、このたった1つの、しかも10頁の論文で博士(31歳)、日本学士院恩賜賞(33歳)、文化勲章(36歳)、ノーベル賞(42歳)、その間京大教授(32歳)、東大教授兼務(35歳)ですから凄いです。WatsonとCrick氏のDNAの二重螺旋構造の発見の論文にいたってはわずか2頁です。紙屑みたいな論文を沢山作っても仕方がないような気がしてきます。しかし、何か見つけてささやかなことでも公表しておけば、どなたかが発展させ、世の中に役立てて下さるかもしれないという儚い夢をもって、やったこと、考えたことは文字にしておいた方がよさそうな気もします。 濱田先生はスポーツが大変お得意で「学問とスポーツは感激するためにある」とよく言っておられましたが、そのようなヴェクトルで捉えると「人生は感激するためにある」と言えなくもありません。ノーベル賞受賞の知らせを聞かれた物理学者が「万歳なんて言えない(嬉しくなんかない)」と取り囲んだ新聞記者に言っておられましたが、同じ事象でも反応は人それぞれ違うはずです。それにしても、私は今まで何をしても達成感がなく、飛び上がって喜べるようなことは今まで一度もありませんでした。せめて松毬に生えるキノコの高さ程度でもよいから天国に飛び上がる前にこの地上で飛び上がりたいと遅まきながら期待して菌遊学を続けています。 うかうかしていると、今村・濱田両先生から「余計なことを書いてないで、そろそろこちらに来ないか」と誘われかねません。黄金の70歳代の後半の高貴高齢期を菌遊で楽しく、そして余計なものを残さないように健康に気をつけて頑張りたいと思います。 千葉県の菌類とはあまり関係のない長い駄文で会員諸兄姉のお目を汚しましたが、自己紹介の場をお借りしてわが国の菌学・菌根学の重要な拠点の興亡の歴史の一端を紹介させていただきました。私の思い違いなどがないとも限りませんので、ご指摘、ご叱責賜れば幸甚です。千葉県菌類談話会会員の皆様にはどうかご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。 なお、関係者のお名前は一部の方を除いて仮名にさせていただきましたが、菌学・菌根学や京大農学部に関わりのある方であれば同定は極めて容易です。どうかご容赦のほどお願い申し上げます。 最後になりましたが、濱田稔先生の写真と資料及び森本彦三郎氏の写真と新聞記事の写しの掲載についてお許しを賜りました先生の御息女の山本純子樣と森本彦三郎氏の御子息の森本養菌園二代目園主森本肇樣に厚く御礼申し上げます。 |
| 文章のはじめに戻る このページのトップへ |
Copyright (C) 1999 Chiba Mycological Club